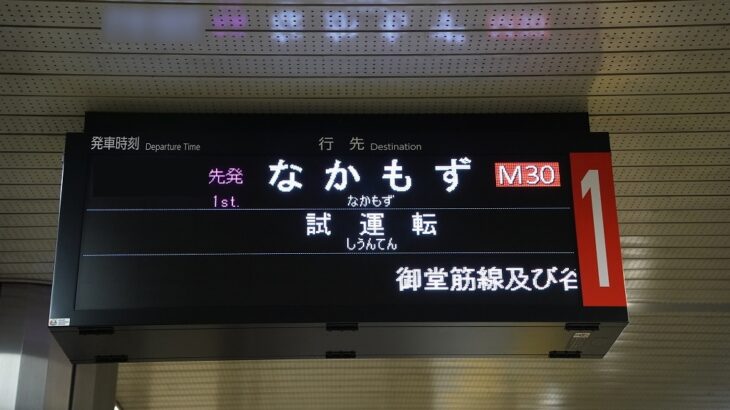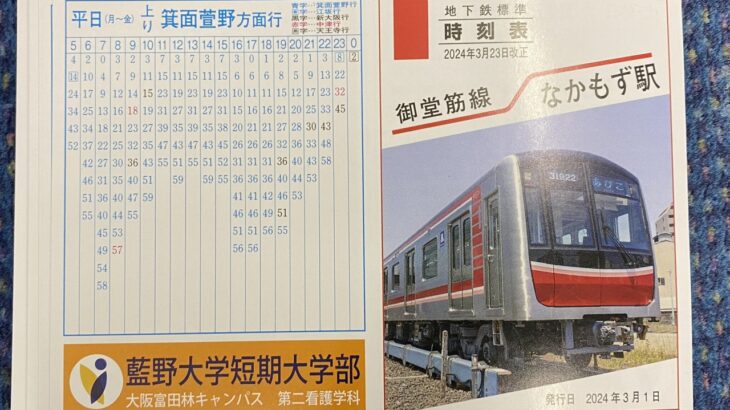これ、どこの駅だろうか。階段上のガラス窓の形から淀屋橋駅やと思うんやけどな… #写真が語る大阪史 #大阪メトロ #昭和史 #昭和モダン https://t.co/AIzOEsVCa4
— 米澤光司(BEのぶ)@昭和史家 (@yonezawakouji) February 19, 2020
「昭和10年の御堂筋線の写真ってよく見るけど、4駅とも同じような地下構造で何駅かわからない〜」ってこと、よくあるよね!!!!!!!!
お任せ下さい!!
今日は大阪地下鉄マニアの私が、その見分け方をばっちりくっきり解説しちゃいます!
本町

出典:大阪市電気局「世界に於ける最近の高速鉄道」、昭和9年
まず、もっとも構造が違うのが本町駅。
3駅がアーチ・ドーム状の構造の中、この駅だけは柱があることで、容易に見分けることが可能です。
梅田
 出典:「大阪市地下鉄建設70年のあゆみ」 出所:http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-237.html
出典:「大阪市地下鉄建設70年のあゆみ」 出所:http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-237.html
梅田駅は、工事に難儀したこともあって完成が2年後の昭和10年にずれ込みました。
このせいなのか、アーチ状の駅部分はわずか4両分程度しか作られず、奥行きのないホームとなっています。

ちなみに、現在梅田駅(北改札)で使用されている照明は、この開業当時のものを復刻・リデザインしたものを使用しています。
梅田を見分けるコツは「遠景があるかどうか」と、現在の梅田駅でも使用されている照明の形です。
残り2駅は…

残るは淀屋橋と心斎橋ですね。
どちらもアーチ状ホームで、かつプラットホーム延長も12両対応(当時の100型の長さで、現在だと9両程度)極めて長い。当時の資料によれば駅ごとに色が違ったそうですが、モノクロ写真ではそれもわからずじまい。
では、この2駅はどこで見分ければいいのでしょうか。
答えは照明にあります。

出典:「大阪市電気局事業概要」. 昭和12年10月
心斎橋駅は、天井からシャンデリアが吊り下げられ、アーチ状屋根の線は2本になっています。
資料によると、ピンク色のタイルによって装飾されていたのだそうです。
(資料:『大阪市営交通90年のあゆみ 39p』(財団法人大阪都市協会,1993年5月20日))

それに対して淀屋橋駅はシャンデリアがなく、屋根中央部に近代的な照明がセットされ、補助的に駅名標部分の上にも照明があるのが特徴です。
また、アーチ状屋根の線も1本になっています。
総論

いかがでしたでしょうか、以上が御堂筋線開業4駅を見分けるポイントになります。
大阪の昭和史をたどる上で欠かせない、大阪市営地下鉄開業。「これは何駅…?」と迷ったら、是非今回ご紹介した「違い」を見て参考にしてみてくださいね。