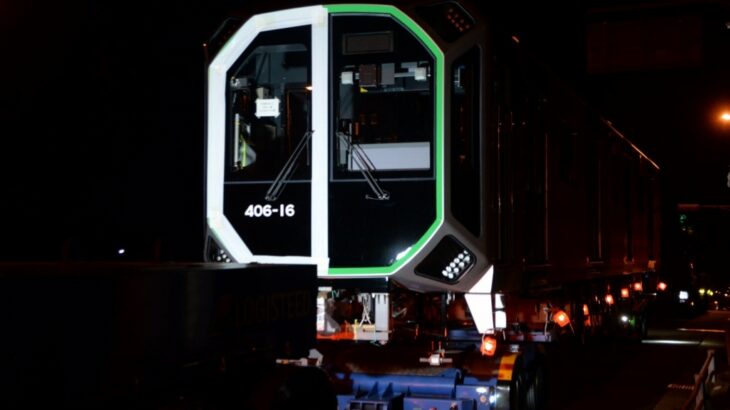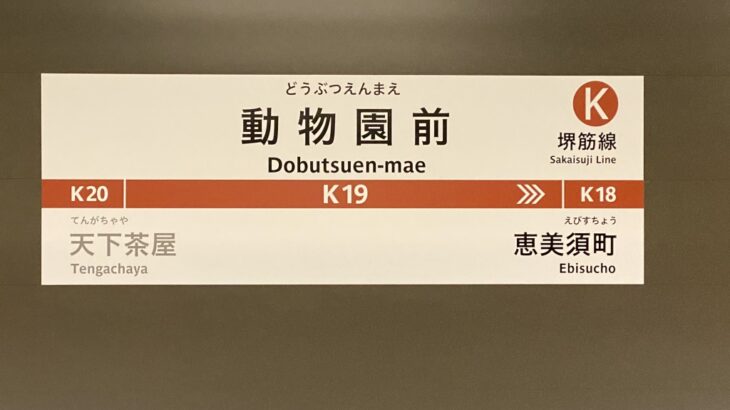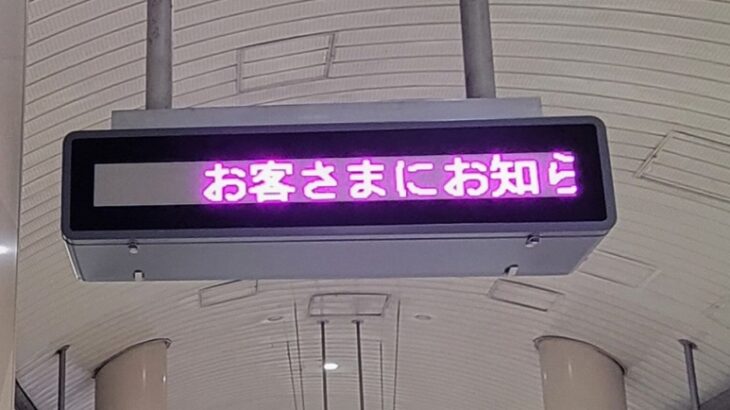停留所…もとい、地下鉄の駅には多様な柱が存在します。
これまで建設技法としては取り上げられることがありましたが、仕上げデザインに関してはあまり見たことがないので、当サイトで取り上げてみます。
タイル張り
現在では姿を見ることはありませんが、かつてよく使われていたのはタイル張りでした。
しかしながら、モザイクタイルバリは剥落が多く、補修頻度とコストの兼ね合いや、予備のタイルが品切れになったこともあって、以下の形式に変わっていっています。
マーベロン張り



タイル張りに変わって、現在比較的多数採用されているのがこのマーベロン張りの柱。
ラインカラー部分には、石粉粘土93%・プラスチック7%の配合で調合した後に平板へそれを流し、固まりかけている半凝固状態になったら、改めて円筒形の型に流して成形する結構凝った作りになっているのだそう。
初採用は、谷町線東梅田~都島間開業時です。
ステンレス巻き


ステンレスの型材で覆ったタイプ。ステンレス車が中心の大阪市営地下鉄では、車両デザインと相まって都市的な感じでなかなか映えるデザインです。
腐食によく耐えるからなのか、平成に入ってからの駅舎リニューアル時によく採用されているようで、開業当初はこのデザインではなかった玉出駅や天王寺駅などで採用実績が見られます。
アルミスパンドレル巻き


谷町線文の里~長原間で見られるアルミスパンドレル巻き。 柱に合わせてアルミの型材を作り、それを電解発色させ、ゴージャスなゴールドカラーに仕上げられています。
この後の鶴見緑地線鶴見緑地~京橋開業時には再びマーベロン巻きへ戻っており、完璧な仕上げ方法を模索しているのか、様々な検討が現在も続けられているものと思われます。
この記事の作者
 記事作成:Series207
記事作成:Series207
大阪市営地下鉄ファンサイト「Osaka-Subway.com」運営主宰。
その他、クレジットカードファンサイト「鉄道ファンのクレジットカードのりば」なども運営中。
★ご案内
日常や当サイトで取り上げないような他の大阪市営地下鉄の話題ならこちら
文章中の写真の著作権は著作者に帰属します。無断転載は固くお断りします。
Photo,Writer : Series207 2017/09/26