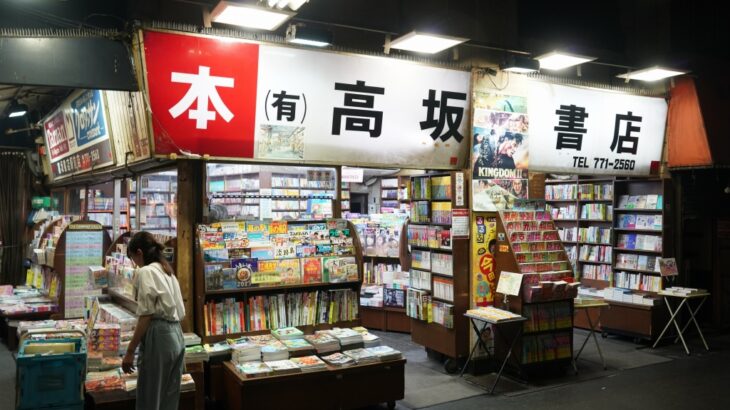先日、千日前線の新深江〜今里間が開業から50周年であることをご紹介しましたね。
実はあの区間は、ちょっと特殊な工法で施工された事をご存知でしょうか。
その名も「凍結工法」です
と、凍結…?
”地盤を凍らせる”

この区間における地下水のある場所より下の土は、最大限まで水で満たされた状態になっていてドロドロになっています。
この水を冷却して凍結させ、常温だと軟弱な地盤でも(凍って固くなるので)安全に穴を掘ることができる…というのが基本的な考え方です。
1962年に大阪市水道局が初めて採用、守口市の新寺方橋の下に上手移動を通るための”さや管”と呼ばれる細い1.8mほどのチューブを通す際に採用されました。
地下鉄にも採用

その後、このノウハウを活かして地下鉄工事にも採用されます。
まず1964年の四つ橋線なんば~四ツ橋間にある道頓堀下の建設の際に補助的に採用、次いで千日前線今里駅付近の建設の際に本格的に採用されたのでした。
今里駅は地下水を非常に多く含んだ地盤が軟弱な場所で、かつ現在でも多大な交通量を誇る今里ロータリーの下、更に当時走っていた路面電車のターミナルや市バス車庫用地もあり、絶対に地盤沈下が許されない土地柄でした。
そこで採用されたのが、この凍結工法でした。
1966年7月21日の2時から17時までの15時間、21000Lもの液体窒素を投入して地盤を凍らせて掘削し、無事成功を収めました。
結局
・3号線(四つ橋線)道頓堀の下
・5号線(千日前線)今里駅下
・4号線(中央線)森ノ宮~谷町四丁目複線シールド部
と、これら3カ所において順調な成果を挙げたことから、軟弱地盤で城東運河を渡る今里~新深江間にも採用されたのでした。
まさかの氷が溶けて水没

城東運河を渡る今里大橋付近は家が密集していて、また道路も1日5万台が走るなど、地上工事を大規模に行う時間や用地がなく、この当時は凍結工法しか選択肢がありませんでした。
現在ではシールドトンネルがあり、この当時もなくはなかったのですが、
軟弱地盤に対する適応力は今と違って弱く、どろどろな今里~新深江間には不向きでした。先述した中央線の複線シールドも、地盤が硬い故に選べた選択肢だったのです。
凍結工法を用いて城東運河直下を固め、順調に工事を進めていっていたその矢先…

1968年9月6日、漏水が異常に増加。なんと凍っていた氷土が溶けて水となり、コンクリートをまだ打っていなかった部分から水が流れ込み、翌7日には完全に水没してしまう大事故となりました。
わかりやすく言うと、こういうことになります。
やめて!凍結工法の力でドロドロな土を固めてるのに、それが溶け出したら、せっかく掘った地下鉄トンネルの中に水が溢れて水没しちゃう!
お願い、溶けないで凍結工法!あんたが今ここで溶け始めたら、鶴橋や今里のトンネルはどうなっちゃうの?
ここを耐えれば、1969年4月の千日前線の初期開業区間として、野田阪神~桜川間と一緒に開業できるんだから!
次回、「凍結工法死す」。デュエルスタンバイ!

水が漏れ出したと思われる区間。
…この事故で鶴橋~新深江間が全て水没。鶴橋→谷町九丁目は上り勾配なのでようやくここで水がストップしたのでした。
当初は千日前線初の開業区間である野田阪神~桜川間と同時期の開業を目指していましたがこの事故で遅れ、谷町九丁目~今里間は一足先の1969年7月25日に開業できましたが、残る今里~新深江間は9月10日にまでずれ込んだのでした。
同区間においては復旧作業が相当手間取った様子が伺えます。
冷凍機の早期停止に伴う凍土の融解により,西側立坑からの漏水が増加し,河底が陥没,大量の河水が坑道に流入した。
事故を報じた当日の新聞によれば,①凍結パイプの1本が何らかのショックで折れて中の冷却液が流れ出し,冷却機能が停止した,②浸水が始まると凍土が融けだし,トンネル上方の河底に穴があいた。
出典:http://www.jgskb.jp/japanese/book/トラブルサム地盤研究委員会報告書.pdf
この事故以来、リスクが大きいからなのか、大阪地下鉄の建設工事においては凍結工法は用いられていません。
今回の記事を書くにあたって軽く調べてもみましたが全くヒットしないことから、地下鉄の工法としては採用に至らなかったものと思われます。(ただし、道路掘削などでは現在でも採用例があるようです)
多様な大阪地下鉄の「穴」

大阪の地下鉄におけるトンネル建設は非常に様々な工法が試みられ、穴掘りの多様性では日本一と言っても過言ではありません。その分、今回のように失敗もまた色々とあります。
他にも小野式隧道工法(動物園前~大国町、上記写真)や、無筋アーチ函形工法(花園町付近)、日本初の複線シールド工法(森ノ宮~谷町四丁目)や3連マルチ工法(大阪ビジネスパーク)などがあります。
この凍結工法の記事は長らく書きたいと思っていた事案なんですが、今回これを書くにあたってネットで探しても全く見つからない歴史だったので、改めてこうして記事にしました。
こういう非常にマニアックなトンネルの掘り方の記事も、需要があればわかりやすく書いていきたいと思います。
参考文献
大阪市交通局「大阪市地下鉄建設五十年史」166p、556-563p