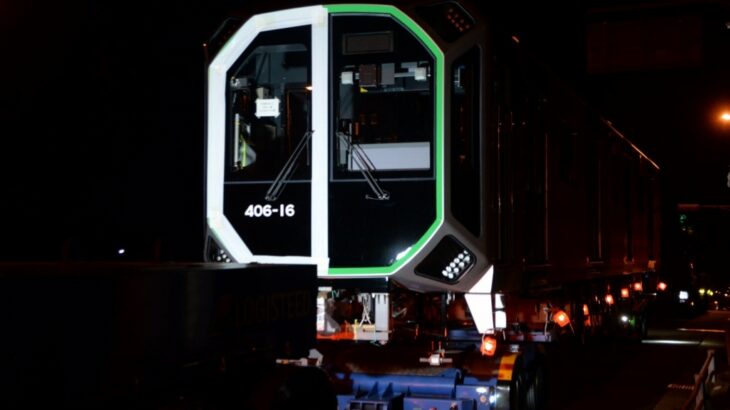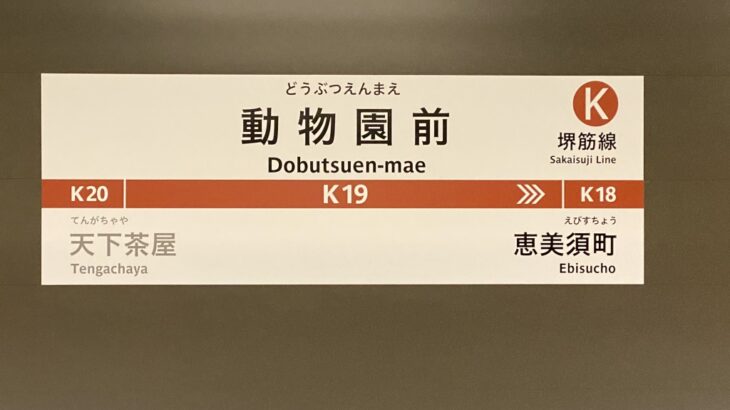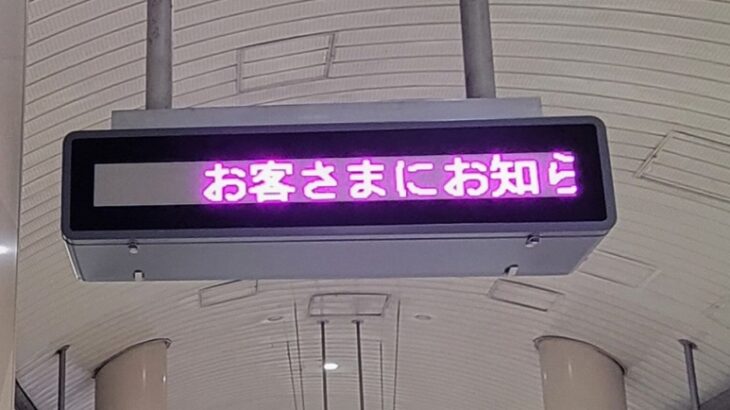大阪市営地下鉄では、全国でも珍しい直流750Vという電気方式を使っています。
これは開業時に「将来的に1500Vを使っている郊外私鉄との直通運転を見込んでいたから」という有名な噂があるのですが、果たして本当のところはどうなのでしょうか。
当時の文献を見てみる
構想当時の大阪市営地下鉄は地下区間が都心部だけの予定で、あとの郊外部分や一部箇所については高架路線で計画されていました。

1号線(御堂筋線)でも地下区間は中津~難波、および天王寺駅のみで、残りは全て高架での建設予定だったのです。

昇圧対応には2種類の案があって、全線1500V化の他にも、高架路線だけT車(転がり台車)にパンタグラフをつけて集電する構想があったのだとか。
T車にパンタグラフを載せて、750Vと1500Vの切替式を予定していたという説と、全線1500Vに昇圧するという説があったようである。
出典:大阪市交通局 1)
当時の100形~500形までの電車には、将来的な1500V昇圧にもすぐ対応できるよう以下の設計がなされていました。
・750Vの主電動機(モーター)2個制御だったが、昇圧時に4個制御へ変更できるよう配線設計の柔軟性が取り持たれていた
・750V時には電動機は2組の整流子、直列抵抗を並列的に接続し、1500Vへ昇圧の際には直列接続するようにしていた。
・集電装置、主要回路は最大耐圧1500Vを考慮して設計していた。
尚この考え方で設計された車両は500形までで、600形以降についてはこの考えを取りやめて750V専用電車として設計が行われて今日に至っています。
電圧が低いと変電所を多く設置する必要があったことから、変電所から遠い駅では加速が悪くなるということもあったそうです。
ということで「郊外私鉄と乗り入れする予定があったから」というよりは、単に「自局線の高架路線で1500Vを使う予定があったから」というのが真相のようです。
昇圧はしない?

実は、現在でも昇圧をしようと思えば出来るようになっているのだとか。
もちろん1500Vに対応した機器への取替などそれ相応のコストはかかるものの、平成6年に発表された文献によれば技術的にも十分対応可能なのだそうです。
それでも昇圧していない理由については別記事で解説していますのでこちらから。
関連リンク
参考文献
- 大阪市交通局「大阪市地下鉄建設五十年史」
- 「サードレール高電圧化に関する調査研究」財団法人 大阪市交通事業振興公社 巖 純二
- 国土交通省「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準」